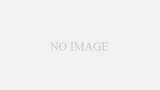この記事を読んでいるあなたは、今の職場を離れたいと思っているかもしれませんね。
新入社員なら、
「3年も経っていないけれど、辞めても問題ないだろうか?」
経験豊富な人でも、
「退職する決心はついたけど、その後の手続きがよくわからない」
など、退職に伴う不安は尽きないものです。
この記事では、特に新卒後間もない「第二新卒」を中心にした、退職の流れや有益なアドバイスを詳しく説明していきます。
ベテランの方でも役に立つ情報はありますよ。
それでは、詳細について見ていきましょう。
第二新卒とは
求人広告で「第二新卒歓迎」という言葉を見かけることがあります。
「第二新卒」とは、公式な定義はありませんが、一般的に「卒業後2~3年以内に転職を考えている人」を指すことが多いです。
新卒で入社して早期に退職した人や、卒業後2~3年以内の人は、第二新卒としての転職活動が可能です。
第二新卒者には、新卒と同様に、そのポテンシャルや成長性が重視されるため、経験が浅いことを心配する必要はありません。
入社3年未満での退職
「最低でも3年は同じ会社に勤めないといけない」
という意見をよく耳にしますが、これは部分的に正しく、部分的に誤っています。
実際のところ、入社3年未満で退職することに特に問題はありません。早期に次のキャリアステップに進むことで、人生の時間を有効に使えるメリットもあります。
一方で、3年未満での退職が問題視される主な理由は、「すぐに辞める傾向にある」という印象がつくことにあります。
第二新卒で、すでに複数回の転職をしていて、履歴書に3年未満の職歴が多く並んでいる場合は、現職で3年以上働くことを考えたほうが良いでしょう。
退職を考える際の理由
「辞めたい」というあいまいな気持ちだけで退職を決めるのは賢明ではありません。
退職したいと思う理由を自分でしっかり整理することが大切です。
理由を整理することで、退職を見直すこともあれば、意思を固めることもあります。
退職の面談の際、多くの場合は上司から引き留められることがあります。
その際には、流れに流されずに、自分の退職の意志をしっかりと持つことが重要です。
人間関係や仕事内容の不一致、業務量の多さが理由であれば、部署変更で解決する可能性もあります。
退職の流れについてのステップバイステップガイド
退職を決意した際には、通常以下の5つのステップを踏むことになります。
- 上司への退職意向の伝達
- 会社からの退職の承認
- 仕事の引き継ぎ
- 有給休暇の取得
- 退職の完了
これらのステップについて、詳しく見ていきましょう。
上司への退職意向の伝達
退職を考えている場合は、まず直接上司に意向を伝えることから始めます。会議室を予約し、面談を設定して話し合いましょう。
この段階で退職願を提出しても構いませんが、まずは面談で退職の意向を伝え、その後に正式な書類を提出する方が、双方にとって良い印象を与えます。
円滑な退職を目指すためにも、退職の意向は慎重に伝えましょう。
会社からの退職の承認
退職願を提出すると、その後社内での手続きが進みます。
上司を通じてその上の管理職に退職意向が伝わり、最終的には人事部の承認を受けて公式になります。
仕事の引き継ぎ
退職が正式になると、次に業務の引き継ぎが始まります。
通常は上司が引継ぎの指示を出します。
引き継ぎ資料は、たとえばExcelで作成し、後任に渡すのが一般的です。
もし引継ぎの指示がない場合でも、良心に従って基本的な引継ぎ資料を作成しておくべきです。
有給休暇の取得
退職日までの有給休暇は通常、一括で取得します。
ただし、会社の方針によっては、週に数日ずつなど分散して取得することもあります。
これは、退職までに業務の引継ぎを完了させる必要がある場合によく見られます。
退職の完了
最終的に退職日が到来します。有給を取得している場合は、退職日に出社する必要はありません。
最終出社日には、同僚や上司に適切に挨拶をすることが大切です。
円満退職のための注意点
退職を考慮する際には、いくつか重要なポイントがあります。
これらを守らないと、会社とのトラブルが発生し、円満退職が難しくなるかもしれません。以下の点に注意しましょう。
直属の上司に退職を伝える
退職の意思は、まず直属の上司に伝えることが重要です。
例えば、課長が直属の上司であれば、部長より先に伝えるべきではありません。
これはビジネスマナーとしての上司への尊重です。ただし、上司の問題行動が退職の理由である場合は、異なる対応が必要です。
「退職願」の使用
特別な事情がなければ、「退職願」の提出をお勧めします。
これは「退職届」よりも柔軟性があり、一度提出しても撤回が容易です。
ただし、状況に応じて「退職届」を使用する場合もあります。
退職承認まで他人に話さない
退職が正式に承認されるまでは、同僚などに相談することは避けましょう。
噂は予想以上に早く広まるため、退職の話は上司以外にはしない方が賢明です。
有給休暇の利用
有給休暇の消化を拒否されることもありますが、これは労働者の権利です。
ただし、会社には有給の「時季変更権」があり、日程の変更は可能です。
必要な場合は労働基準監督署への相談も検討しましょう。
退職後の転職活動での注意点
未定の転職先で退職することは珍しくないですが、退職後の無職状態での転職活動には注意が必要です。以下の点に注意してください。
アルバイトや派遣への依存を避ける
無職という状況では収入が途絶えます。特に第二新卒では貯金が少ないことが多いため、転職活動が長引くとアルバイトや派遣へ頼ることがあります。
しかし、フルタイムの仕事をすると転職活動に必要な時間が確保できなくなる可能性があります。
貯金の減少による焦りを避ける
収入がなくなると貯金が減少し、焦りが生じる可能性があります。
この焦りが適切な転職先の選択を妨げ、結果的に望まない職場に応募することになりかねません。
このような状況は、新しい職場での早期離職につながるリスクがあります。
転職活動のタイミングと戦略について
転職活動では、現職を保ちながら次の仕事を探す方法が金銭的安定や心理的余裕をもたらします。
頻繁な転職には大きな労力が必要なので、可能ならば現職のまま次の仕事を見つけるのが望ましいです。
もし現職を退職してから転職活動を始める場合は、最低1年分の生活費を貯えておくことを推奨します。
心理的に限界を感じている場合は、無理せず退職を選択することも重要です。
自己負担が大きい人は、限界を迎える前に退職を考えるべきです。
周囲のサポートがあれば、退職を決断しやすくなります。
体調に異常を感じた場合は、迅速に医療機関の受診をお勧めします。
さらに、精神的な問題を抱えている場合には休職を検討することもできます。
休職は一時的な対策であり、必ずしも復職が必要なわけではありません。
休職中に転職を検討し、復職が困難と判断した場合は、休職期間の終了と同時に退職することも選択肢の一つです。
休職中は傷病手当金を受け取ることができるため、無給の状況を避けることが可能です。
休職期間を活用して転職活動を行うのも良い戦略と言えます。
休職の手順
休職を考えている場合、手続きは次のように進めます。
医師の診断書を取得
体調不良を感じたら、まず病院で診断を受けます。
精神的な問題が原因の場合は、休職用の診断書が必要であることを医師に伝えると、大抵の場合で診断書が出されます。
重い病状の場合、医師から休職を勧められることもあります。
上司と休職の相談
診断書を持って上司に休職の希望を伝えます。精神的な限界が近い場合は、上司から休職を勧められることもあります。
ただし、勤務年数や会社の規定によって休職の可否が異なるので、就業規則を確認してから相談します。
休職届の提出と休職の開始
上司との合意後、休職届を提出します。
出社が困難な場合は郵送で行うこともできます。通常、休職届と一緒に診断書も提出します。
復職か退職の選択
病状が改善されれば復職届を提出して仕事に戻ります。
退職を選ぶ場合は、退職届を提出します。
休職期間終了時に自然退職になることもあり、その際は同意書に署名するだけで済む場合もあります。
退職プロセスの新しい選択肢と転職観の変化
直接上司に退職を伝えるのが難しい場合や、すぐに職を離れたい状況で「退職代行サービス」を利用することが増えています。
このサービスでは、一定の料金で退職手続きを代行してもらえます。
現代では、一つの会社に長く勤め続けることが必ずしも好まれなくなっています。
終身雇用の概念が変化し、転職経験がないことがスキル不足と見なされることもあります。
これは「一つの会社では多様な経験が得られにくい」という認識から来ています。
退職や転職に対する偏見は減少し、自分のスキルや価値を高め、多様なキャリアパスを探求する時代になっています。